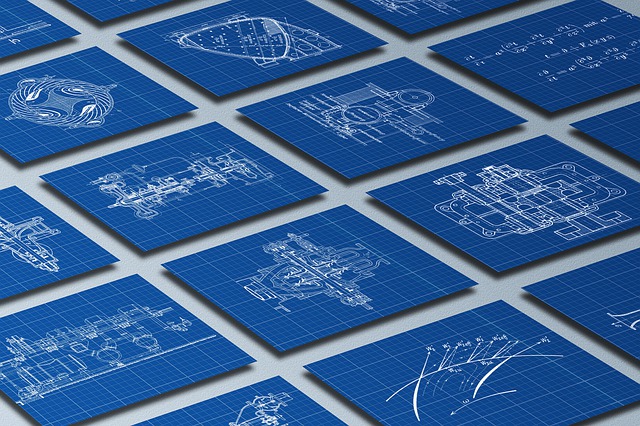
今、業界のトレンドはこの分野ですべての分野に必要なエンジニア。あらゆる物がデジタル化している中でその需要は大きく、業種も職種もやる事も様々。
目次
1.電気の分野は大きく二つに分かれる
2.なぜ今電気エンジニアが求められている?
3.電気エンジニアの将来性
4.メリットとディメリット
まず電気の世界を大きく2つに分けると電気と電子に分かれます。何が違うのか・・・
強電と弱電で分ける人もいれば、電気とはハード、電子とはソフトと定義する方もいます。
どちらも正解で、電気は主に動力源と成り得るものやその設備での仕事が多く、電子では機械を動かす頭脳を作る仕事が多く存在します。
この両方ともに仕事が無くなる事は考えにくく職種としては安定していると言えます。
これはどの業界でも言える事ですが、高齢化によって担い手が減少しています。
しかし世の中の製品の殆どが電気で動く時代。技術者の需要は高水準を維持しています。
特に東海地区では自動車関連企業が数多く存在し、二酸化炭素の排出量を減らす意味でも電気自動車の普及・促進は自動車業界では最も重要なテーマです。
また他の業界でも電気使用量の逼迫を受け、省電力化は避けては通れない開発テーマと言えます。
モノ作りの世界では最も忙しく様々な業種で必要とされています。
回路設計や配線等々、電気の業界はAIでは難しい業務が多々あります。効率化でAIが一部の業務を担うことは考えられますが、ハード分野ではAIを使う側の設計と成る為、業務が無くなる可能性は低いと考えられます。就職・転職したとしても失敗は少い安定した業務と言えます。
ロボット、電気自動車、ドローン、IoT機器、VR機器…等々開発競争は激しさを増しており企業も先行投資の意味で新規採用も積極的に行っています。
また、インフラ関係の業務も設備の点検や修理・メンテナンスは必ず発生します。そういった部分でも長く安定した職種と言えます。
1人で開発を進める事はまず無い事から、打合せや調整業務が多く発生します。
その中で必ず納期を考えながら業務を進めていく事になります。
スケジュールがタイトになればそれだけ仕事の負荷が増える事になります。また、途中で設計変更が生じやり直しという事もしばしば。
納期に間に合わせる為に残業を・・・なんてことも。

